
こんにちは、はっちです^^
芝生をDIYで植えてもう2年経過しました。その間にどんどん芝生は少しずつですが広がっていってくれるのですが、広がりすぎてもあまり都合が良くなかったりします。
そして、広がってしまった後はその処理も大変。
今回は芝DIYで育てた芝を決められた場所で食い止めていきたいと思います。
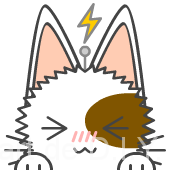
芝の成長力は侮れません。放置しておくとどんどん広がっていってしまいます。
芝生の強い繁殖力。余った材料で芝止めDIY
当初の芝生はもうほとんど枯れているのではないか、という状態でしたが、その後順調に緑が広がっていきました。

芝は最初に土を掘り返して、柔らかくしたところしか成長しないかな~なんて思っていましたが、カチンカチンの土の場所にもどんどんランナーと呼ばれる茎を伸ばしていき、どんどん勢力を伸ばしていっています。
芝が広がってもいい場所についてはどんどん緑が増えていくので良いのですが、その過程はあまり見栄えのいいものではありません。

また、我が家の場合、浄化槽が隣りにあるため、あまり芝が侵食していくのはよくありません。

浄化槽はFRPというとても丈夫な材質で作られているため、穴が空いたりはしませんが芝が入り込み、蓋が持ち上がってしまったり。また開かなくなってしまう可能性もあります。
こうなってしまう前になんとかしておくべきでした。
有り合わせの材料で芝止めを埋めてみよう。
今回はちょっと広がりすぎてしまった芝を取り除き、芝止めを入れることにします。
まずは芝を取り除くのですが、芝は良く”剥がす”という表現を使います。
どうやって剥がすの?と思ってスコップを入れてみると。

剥がれました^^(結構力がいります。)

芝は根が浅い位置に張られるため、こんな感じで剥がれていくのですね。
綺麗に切り込みを入れて剥がしたわけではないので汚いですが、なんとなく売られているようなロールの状態にしてみました。
意味はありません^^;
浄化槽の周りはそうはいかないので、ひたすら手で抜いていきます。

ちなみに、時間はかかりますが、除草剤を使っても大丈夫。
使用した薬剤はグリホサートという100均などでも売っている除草剤でしたが、かけた場所だけ枯れてくれました。

これまた見栄えは良くないですけどね。
農薬ではありませんので使用する場所に注意です。
芝が広がりすぎる前に芝止めで範囲を限定
必要の無い部分の芝生を抜いたら、次に芝止めを埋めていきます。
芝止めは普通にホームセンターでも売っています。
当初、芝止めはウッドデッキ作りなどで余った端材を適当に埋めていたのですが。(写真中央から右手側の木材)

ここはまだ食い止められているのですが、完全に越えられてしまっている場所もありました。
どうやら芝は表面をランナーで伸ばして勢力を広げるのと同時に、地下茎でものばしていくようです。
先程の芝を剥がした写真を見ても、地下部分は5~10cmほどは伸びている様子。

ですので芝止めを埋める深さもそれぐらい必要だと思います。
もし越えられてしまっても、その時はその時。早めに対処しておけば勢力は広がりませんし、芝としても越えにくい場所は嫌がると思います。
オンデュリンの屋根材を使用した芝止め
以前、物置を作った時の屋根材が余っていました。

こちらの屋根材はアスファルトのような材料で作られており、とても耐久性が高く丈夫なのに加えて、のこぎりなどで切れるため扱いが容易です。

今回は、こちらをブラックアンドデッカーの丸のこでカット。普通にのこぎりでもがりがり切れます。

ただ、刃長が無いため半分しか切れませんでした(汗)
ので、同じ線に沿って裏側からもカット。
できました。

これを、芝生にしたい境界に埋めていきます。

スコップで溝を掘って、差し込んでいき、固定も兼ねて石コロ投入。

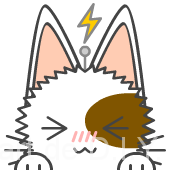
少々ガタガタですが芝が伸びると黒い境が目立たなくなります。
別の材料でも代用は効きそう。
他にも候補として、トタン、ポリカ、レンガなどを考えましたが、これが一番楽で、破損がしにくいかなと思いました。
見栄えも考えればレンガが色々アレンジしてみると面白い感じになりそうです。

こんな感じにできるとかっこいいですね。
芝の広がりを抑えることは重要
芝は非常に成長力が強く、どんどん広がっていきます。
土が無ければいかないと思いきや、防草シートの上もずんずん広がっていこうとします。
しっかりと緑が出て綺麗な状態では芝は美しいのですが、あまり手がかけられていないと、周辺にどんどん伸びていき、放置されているように見られてしまいます。
ある程度芝にする範囲を決めて、しっかりと管理していくことが、綺麗な庭としても大事なだと思います。

多少の苦労はありますが、芝の緑はやっぱり癒やされますので、庭に管理できる範囲で植えるのはおすすめです。
それでは(^O^)/
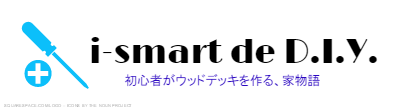



コメント